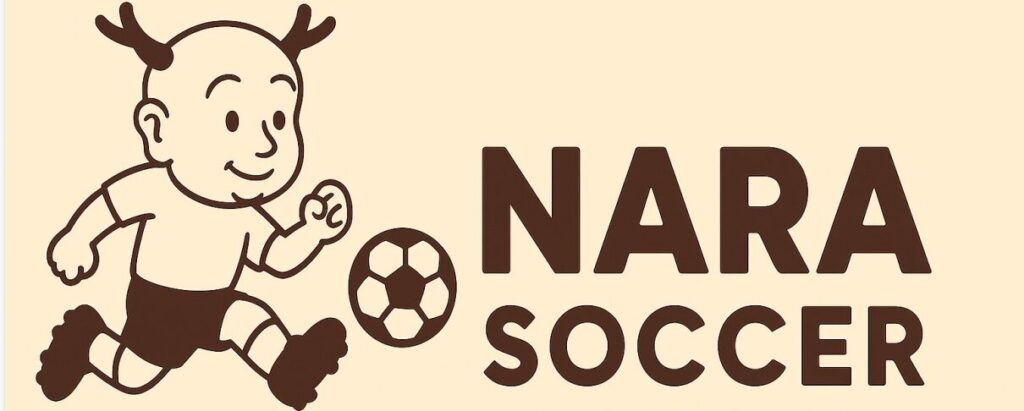お子様がサッカーをしているということは、おそらく父親か母親が小学生時代大なり小なりスポーツチームに所属経験がある方が多いと思います。
実際当時の経験がお子様の役に立つことはたくさんあると思います。
ですがたとえサッカー経験者であっても「8人制」「指導者へのライセンス推奨」「クラブチームの拡大」「取り巻く環境」など多くの違いがあります。
私自身が息子と学んでいく中で気が付いたこと、調べたことを随時投稿していきます。
Contents
最初に皆様に知っていただきたいこと
チームはお子様が「理不尽を学ぶ」最高の場所

家庭や学校であれば、親や教師が配慮しお子様がある程度自由にふるまっても「平等」に機会が訪れ、場合によっては「優遇」されます。
しかしチームにおいては「本人の人柄」「実力」「取組姿勢」など様々な事柄が加味され明確にランク分けされます。
本来は社会に出るまで経験することがない「理不尽」に見舞われ、お子様は強いショックを受けると思います。
私の息子の場合
私の息子は7歳でサッカーをはじめたのですが「小柄」で、特に運動経験もなかったため「パスがもらえない」「ボールに触れない」などある意味「あるある」の経験をして当初かなりの衝撃を受けたようです、時には親が助言もしましたが「コーチに質問する」「チームメートに自分のできることを伝える」「自分のできることをプレーでアピール」するなど日々試行錯誤しているようです。
日々の成長
サッカーを始めてから明らかに「癇癪」を起こすことが減り、自分の要求を通すためにはどうすればいいか。
希望や要望があればはっきり伝えるなど、大人になってもできていない方がいるようなことも、できるようになってきたと感じています。
自身で理不尽に立ち向かう力
学生が終わり社会に出れば、おそらく理不尽なことの連続になるはずです。
クラブチームは親や指導者の目に届くうちにわかりやすい理不尽に遭遇したくさんの助力を受けて立ち向かう最高の機会です。
チームがあうあわないを判断は長い目で

移籍や退部は慎重に
「指導者が気にかけてくれない」、「チームにフィットしない」などで退部するのは長い目でみてください。
たとえ合わなくても、体験入部やたくさん調べて選んだチームです、一度退部してしまうと復帰するにも気を使います。
他のチームでフィットするとも限りません、お子様や親御様の「考え方」や「資質」の問題があるかもしれません。
移籍しなくてもレベルアップできる
うまい子供ほど、もっとレベルの高いチームに「身を置きたい、置かせたい」と考えるのは当たり前のことかもしれません。
またお子様が「井の中の蛙」状態になっているならなおさらです。
選手登録なく練習参加できるチームは結構ある
別途取り上げますが、チームレベル底上げのために練習参加のみで選手登録しなくてもよいクラブチームは増えています。
指導者に理解があれば、他クラブの練習に参加し得たものをチームで振うことも十分可能です。
また「奈良県トレセン」への推薦などを考えれば、今のチームの中核選手として推薦をもらう手もあります。
環境が実力を左右する
もちろんトレセン選抜レベルまで行けば、移籍も候補に考えてよいと思います。私が小学生のころ所属していたチームでもトレセン選抜後「強豪クラブ」に移籍し最終的にJリーガーまで上り詰めて選手もいます。
ですがサッカーは自身をチームにフィットさせることも求められます、今後キャリアを積んでいくにあたり指導者はコロコロ変わります。学校の部活であればどんなに「外れの指導者」でもおいそれと移籍できません。
教員指導者の中には「本当に」「本当に」「本当に」どうしようもない指導者もいます。
逃げるべきチーム
矛盾するが逃げるときは逃げる
長い目で見てとはいっても逃げるべきチームも存在します。
所属するだけでお子様にマイナスになるようなケースは逃げてしまいましょう。
指導者の発言に「否定発言」「ネガティブ発言」が多い(子供の考える力を奪う)
中高部活レベルの教員顧問ではまだまだ存在しますが、クラブチームではライセンス取得時に指導を受けるため、ほとんど見かけなくなりましたが。
ですが少数ながら「コーチング」と「否定」を混同している指導者は確実に存在します。
間違ったことを叱責できない指導者はまず失格です。
ですが自身の考えを子供たちに押し付け、考える機会を奪ってしまう指導者は「最低」です。
指導者には「サッカーの指導者」である前に「教育者」として子供を預かる責任があります。
練習参加・見学の段階では見抜けないかもしれませんが、たまにはお子様の練習・試合を最初から最後まで見届け、指導者の発言や指揮に注意してみるのも親の責任です。
子供を叱れない、無視する。
子供が楽しそうに練習しているのは良いことです、ですが野放し状態になっているかどうかには注意を払う必要があります。
遊びの延長で所属しているのであれば問題ないのですが、親として何らかの目的をもって入部させているのであれば、コーチにしっかりヒアリングし改善するつもりが見られなければ、「移籍」や「別のスポーツ」をお子様に勧めてみてもよいかもしれません。
環境と認識の変化
私たちが小学生のころと比べ、環境や考え方は大きく変わっています。
「全国大会=読売ランド」という認識の方も多いのではないでしょうか。(年齢ばれますかね?)
サッカーについても「習い事」の一環として定着し、まっとうなチームであればライセンス保留の指導者が当たり前になり、育成年代を指導するにあたり最低限の基礎知識を有した「教育者」としてのコーチが普通になりました。
公務員である教員よりはるかに、「教育者」として子供たちに接しようと努力・意識されている方々が本当にたくさんいます。
ただ息子の練習試合を見に行った際に、眉を顰めるような発言や指導をしている指導者がまれにいることも事実です。
お子様の人格形成に影響のある育成年代だからこそ、指導者選びはいろんな意味で慎重に無理なく行っていただきたいです。