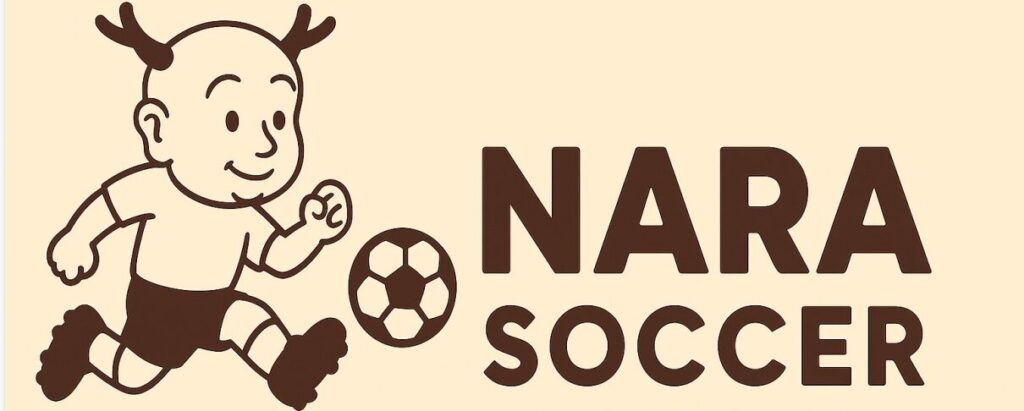Contents
広陵高校野球部の問題から考える、日本のスポーツの未来 ― なぜサッカー界の「セーフガーディング」が子どもを守る最後の砦なのか?
はじめに
2025年夏、高校野球の名門、広陵高校野球部で明るみに出た部員間の暴力事案は、甲子園出場中の辞退という異例の事態に発展し、日本社会に大きな衝撃を与えました。この問題は単なる一個人の不祥事ではなく、勝利至上主義の陰で長年見過ごされてきた、子どもたちの人権がないがしろにされる日本のスポーツ界の構造的な課題を改めて浮き彫りにしたのです。広陵高校野球部の一件は氷山の一角であり、同様の問題は他の多くの競技、特に旧来の指導文化が根強く残る現場にくすぶり続けている可能性があります。
一方で、同じスポーツ界でも、子どもたちをあらゆる暴力やハラスメントから守り、安心・安全な環境でスポーツを楽しむ権利を保障する「セーフガーディング」という考え方に基づき、先進的な取り組みを続ける組織があります。それが、日本サッカー協会(JFA)です。
本記事では、広陵高校野球部で起きた問題を起点とし、JFAが実践するセーフガーディングの具体的な取り組みを紐解きます。そして、それがなぜ、これからの時代に子どもたちがスポーツを始めるうえで、特にサッカーが他のスポーツよりも優位性を持ちうるのかを明らかにします。
セーフガーディングとは何か? 広陵高校野球部の問題を防ぐためのJFAの本気度
セーフガーディングとは、子どもや弱い立場の人々の尊厳を傷つけたり、危険にさらしたりすることのないよう、組織として取り組むべき責任のことです。JFAはこれを「子どもたちがサッカー、スポーツを安心、安全に楽しむ権利とその環境を守るための取り組み」と定義し、その理念を「JFAセーフガーディングポリシー」として明確に文書化しています。
このポリシーは、広陵高校野球部のような閉鎖的な空間で問題が隠蔽されるのを防ぐための、具体的な仕組みを伴っています。JFAの取り組みの「本気度」は、その施策に明確に表れています。
明確な指針と「ゼロ・トランス」
JFAは「あらゆる暴力・暴言・差別・ハラスメント・誹謗中傷を排除する」という「ゼロ・トランス(不寛容)」の原則を掲げています。これは、いかなる理由があろうとも、暴力や暴言を容認しないという強い決意の表れであり、広陵高校野球部で見られたような部員間の力関係を背景とした不適切行為を許さない姿勢を示すものです。
誰でも利用できる「暴力等根絶相談窓口」
JFAは、サッカーの現場で起こる暴力や暴言などの問題を解決するための具体的な仕組みとして、「暴力等根絶相談窓口」を設置しています。この窓口は、選手本人だけでなく、保護者や関係者など、誰でも利用することが可能です。電話またはJFA公式サイト内の専用フォームから通報ができ、直接的な暴力だけでなく、暴言、脅迫、威圧といった行為も対象となります。通報は原則実名ですが、匿名でも受け付けられており、被害者が声を上げやすい環境を整備し、問題が隠蔽されることなく、組織として対応する体制が整えられているのです。広陵高校野球部の事案のように、問題が内部で解決されずに外部からの告発で発覚するケースとは対照的です。
ライセンス制度の徹底と指導現場の質の担保
JFAが先進的な取り組みを進めているからといって、サッカーの現場からハラスメントが一掃されたわけではありません。団体競技である以上、問題が発生する可能性は常にあり、旧態依然とした指導が残る現場も存在します。
だからこそJFAは、指導者の質を組織的に担保するための具体的なアクションとして、指導者ライセンス制度の徹底に踏み切りました。2024年度から、JFAが主催するすべての公式戦において、ベンチ入りして指揮を執る指導者に、最低でもD級以上のJFA指導者ライセンスの保有が義務付けられたのです。
これは、最も身近な存在である小学生年代(4種)のチームも例外ではありません。「お父さんコーチ」のようなボランティア指導者であっても、ライセンスを持たなければ公式戦でベンチに入り、采配を振るうことができなくなりました。
これは、広陵高校野球部の問題が起きた高校野球をはじめとするアマチュア野球の世界に、指導者に対する統一された必須のライセンス制度が存在しない点と極めて対照的です。 野球界にも指導者向けの講習会などが皆無なわけではありませんが、指導にあたるための必須条件とはなっていません。つまり、現場に立つすべての指導者がセーフガーディングについて学んだという制度的な担保がなく、個々の指導者の資質や経験にすべてが委ねられているのが実情です。サッカーにおけるライセンス必携化は、不適切な指導者を最初から現場に立たせないための、制度的なフィルターとして機能しているのです。
なぜサッカーは先行できたのか? 広陵高校野球部に代表される野球界の体質との比較
なぜサッカー界は、他のスポーツに先駆けてこのような取り組みを進めることができたのでしょうか。そこには、広陵高校野球部に象徴される野球界の歴史的背景との違いがあります。
明治期以降、富国強兵の国策のもとで学校教育に取り入れられた体育は、軍事教練と密接に結びついて発展しました。特に、野球は学生スポーツとして早くから普及し、その精神論や上下関係を重んじる文化は、軍隊的な組織論と親和性が高かったと指摘されています。この「軍隊的」体質は、指導者への絶対服従や、精神論の名の下での体罰を容認する土壌となり、広陵高校野球部の問題が示すように、現代に至るまで根強く残っている側面があります。
一方、サッカーが日本で本格的に普及し始めたのは戦後であり、プロリーグ(Jリーグ)が発足したのは1993年です。この「歴史の浅さ」が、旧来の軍隊的な指導文化から距離を置き、世界基準の指導法や選手育成システムを取り入れやすい環境を生んだと考えられます。選手育成においても、幼少期からプロまで一貫したフィロソフィーの下で選手を育成する文化が根付き、セーフガーディングのような包括的な理念も浸透しやすかったのです。
育成年代でサッカーを選ぶことの優位性
これらのJFAの取り組みとサッカー界の文化は、これからスポーツを始めようとする小学生年代の子どもたち、そしてその保護者にとって、野球をはじめとする他のスポーツに対する明確な「優位性」を示しています。広陵高校野球部の問題を受けて、この優位性はより一層際立ちます。
- 「安全」が組織的に担保されている
広陵高校野球部の一件は、個々のチームや指導者の倫理観だけに頼ることの危うさを示しました。JFAのセーフガーディングポリシーと必須のライセンス制度、そして相談・通報窓口の存在は、組織として子どもたちの安全を守る仕組みが機能していることを意味します。万が一問題が発生した場合でも、声を上げ、解決を求めるための具体的な手段が用意されている安心感は、他のスポーツにはない大きなメリットです。 - 子ども主体の「楽しむ」環境
「Players First(プレーヤーズファースト)」の理念は、子どもたちが勝利至上主義のプレッシャーから解放され、純粋にサッカーを楽しむことを後押しします。怒声や罵声が飛び交う環境ではなく、子どもたちの自主性やチャレンジを尊重する指導が奨励されているため、子どもたちはのびのびとプレーし、サッカーを通じて自己肯定感を育むことができます。 - グローバルスタンダードな価値観
JFAのセーフガーディングは、FIFA(国際サッカー連盟)などが推進する世界的な潮流に沿ったものです。サッカーを通じて、暴力やハラスメントを許さないという人権意識や、多様性を尊重するグローバルスタンダードな価値観を幼少期から自然に身につけることができるのは、将来国際社会で生きていく子どもたちにとって計り知れない財産となるでしょう。
結論
広陵高校野球部の問題は、日本のスポーツ界が旧態依然とした指導文化から脱却し、子どもたちの人権を守るという原点に立ち返るべきであることを痛切に示しました。その変革のモデルケースは、すでに日本のサッカー界に存在します。
JFAが地道に、しかし着実に進めてきたセーフガーディングへの取り組み、そして指導者ライセンス必携化という具体的な一歩は、サッカーという一競技の枠を超え、日本のスポーツ文化全体が目指すべき未来の姿を照らしています。保護者が我が子にどのスポーツを選ばせるか考えるとき、単なる競技の人気や強さだけでなく、「そのスポーツが、広陵高校野球部で起きたような悲劇を繰り返さないために、どれだけ子どもの安全と人権を本気で守ろうとしているか」という視点が、今ほど重要になっている時代はありません。その意味で、JFAのセーフガーディングは、子どもたちの健やかな成長を願うすべての親にとって、最も信頼できる羅針盤となるはずです。